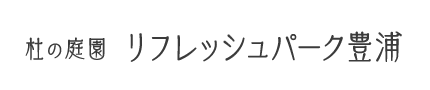春、日本の国を桜色に染めて、風と共に去っていく桜前線。
桜にまつわる文化は、日本の春の風物詩・・・
下関での今年の桜開花宣言は、3月27日の桜の日のこと。
それから10日が過ぎ、例年より長い満開の季が続いています。
❝杜の庭園リフレッシュパーク豊浦❞のある川棚の里も、
まるで桜の雲のたなびきのなかにあるような美しさです。
今日の強風でちらちら散る桜の花びらにも風情があります。
このまま、今週いっぱいは桜吹雪が楽しめそうです。

日本人は、桜を愛する国民。この文化の始まりはいつから?
日本の桜の野生種の代表は、山桜、江戸彼岸・大島桜の三種。
江戸時代までは、花見といえば、なかでも山桜でした。
また、同じ春の花でも、梅や桃は中国から持ち込まれた植物。
平安中期になると、国風文化の影響で、自生している桜を
愛でようという機運が強まり、儀式や行事に
桜が用いられるようになっていったのです。
春の花といえば桜といわれるようになったのは「古今和歌集」
編纂のころから。桜を愛でる文化のルーツはこのあたり・・・
そのなかでは、桜の歌が七十首も詠まれています。
それとともに、このころに桜の栽培品種も誕生。
それが、❝枝垂れ桜❞。江戸彼岸の突然変異といわれています。
大島桜が広まるには、室町時代まで待たなければなりません。
伊豆諸島から鎌倉へ、そして京都へと、大島桜の旅は続きます。
現在では、桜といえば❝染井吉野❞。その発祥は、江戸時代。
山桜の苗木生産がおこなわれていた染井村(豊島区駒込)で、
江戸彼岸と大島桜の種間交雑接ぎ木苗として誕生しました。
そのクローンが明治以降、全国に植樹されていったのです。
他の桜が苗から開花まで10年かかるところを、
染井吉野は2年で開花。その成長の早さと大きな花の美しさが、
普及の要因だと思われます。
なぜ、私たちはこんなにも桜に魅了されるのでしょうか。
ひとつには、長かった冬が終わり、春の到来を告げる花。
ふたつには、年度初めのスタートの春を象徴する花。
みっつめは、ぱっと咲いて、ぱっと散る儚い花であること。
そこれらいのちのはかなさの美学を感じるからのようです。
そんなストーリーを感じながら、リフレで花見・・・
いかがですか。
庭園長 国司 淑子(くにし としこ)
。